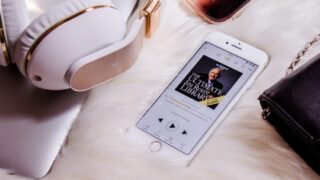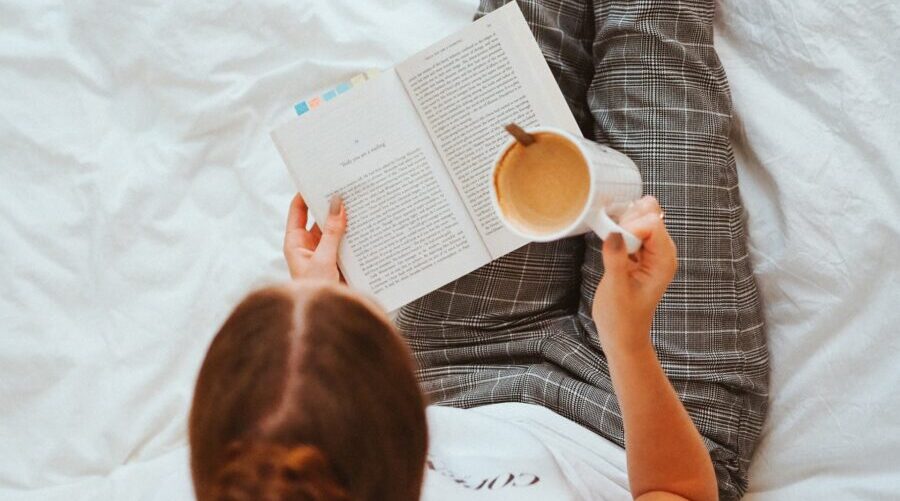読書好きな人にとって、本は最高の娯楽ですよね。
しかし、いつも本を読まない人が「読書の何がいいの?」と思ってしまう気持ちもわかります。
読書する目的(意味)は人それぞれで、娯楽として楽しむのもアリだし、仕事・プライベートを充実させることもできる。
読書の効果を理解することで、本を読むのが苦手な人でも「読書ってありかも!」と思い、本を手に取りたくなるはず。
僕は小学生の頃から読書が好きで、それなりに本を読んできたので、その経験から「読書で得られる効果」について解説します。
読書のメリット7選

読書のメリットは、以下のとおりです。
- 視野が広がる
- 教養が身につく
- 語彙力が上がる
- ストレス解消になる
- 集中力がアップする
- 想像力が鍛えられる
- 脳のアンチエイジング
1つずつ見ていきましょう。
①:視野が広がる
本を通して180度違う考え方や生き方などを知ることができ、視野が広がります。
ふつうに生活していると、他人の価値観に深く触れられる機会はそう多くありません。
他人の考え方を知ることで、別の視点からも物事を考えられるようになり、柔軟な思考ができる。
さまざまな角度から物事を判断できれば、どんな壁にぶつかっても解決へと導けるでしょう。
逆に、1つの視点しか持っていないと、その問題に固執してしまい時間や労力を無駄にする可能性が高いです。
視野を広げるためのポイントは、食わず嫌いせずに雑多なジャンルの本を読むことです。
②:教養が身につく
本を読むことで、普遍的な知識が身につき、それが教養へとつながります。
と言うのも、著者が一生をかけて培ったスキルや、一握りの人しか体験できないようなことを、本を通じて体験できるから。
教養とは、不安定で変化の激しい現代を生き抜くための「武器」で、どんな時代でも通用する本質的・普遍的なことです。
これからグローバル化がますます進んでいくので、教養は身につけておきたいですね。
③:語彙力が上がる
本を読むと普段使わない言葉にたくさん出会うので、語彙力が上がります。
意味のわからない言葉に出会ったら、ググって調べる。その繰り返しで、自然と語彙力が鍛えられていきます。
語彙力とは、どれだけ多くの言葉を知っていて、使いこなしているのかという能力のことです。
語彙力は、仕事や人間関係、プライベートなど幅広いシーンで役立つ必要不可欠なもの。
読書する習慣がある人は、語彙力が高く自分の考えや意見などを論理的に伝えるのが上手です。
本だけでなく、ふとした会話で気になった言葉があれば、スマホですぐに調べる癖をつけましょう。
④:ストレス解消になる
ストレス解消と聞いて、読書を思い浮かべる人は少ないかと思います。
ですが、読書にはストレス軽減効果があると大学の研究で分かっています。
たとえば、筋トレや音楽を聴く、ゲームをするなど、さまざまなストレス解消法があります。
こられと比べて、読書はたった6分で68%もストレスが軽減されたそうです。
本の物語世界に没頭することで、現実のストレスを忘れることができますよ。

⑤:集中力がアップする
読書は集中力が必要です。
本の内容をしっかり理解するためには、かなりの集中力がいります。
今まで本をたくさん読んできた人は、すでにかなりの集中力がついているはず。
さらに、読書習慣がある人は、「仕事や勉強に集中して取り組める」という当たり前のことをしっかりできる人が多いです。
本を読めば読むほど集中力は高まり、自分の世界に入るのが簡単になっていきます。

⑥:想像力が鍛えられる
本を読むことで想像力が鍛えらます。
と言うのも、本は漫画と違い文字だけの情報を頼りに、自分の頭で想像して読む必要があるから。
たとえば、本を読むとき、主人公の気持ちや登場人物の人間関係などを想像しているかと思います。
そのため、同じ作品を読んでも人それぞれ感じ方や作品に対するイメージはかなり違ってきます。
想像力のある人は、気が利いて危機察知能力が高く仕事が早い、といった傾向があります。
つまり、相手の気持ちに寄り添える素晴らしい人になれる可能性がグッと高まりますよ。
⑦:脳のアンチエイジング
本を読むことで、脳を活性化され老化を防いでくれます。
筋トレを定期的にしないと筋力が落ちるように、脳も鍛え続けないと衰えます。
本を読むことで、新しい情報に触れ脳を活性化させることができますよ。
読書を習慣化して、人生の質を上げていきましょう。

読書のデメリットは?
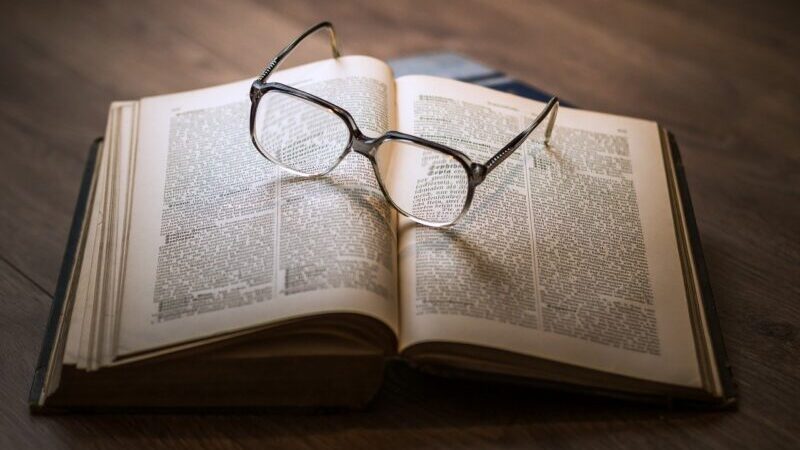
読書はメリットだけでなく、少なからずデメリットもある。それは、「時間」と「お金」がかかることです。
読書すると、1冊読むのに早くても2〜4時間ほど、遅いと5〜8時間くらいはかかるでしょう。
となると、最近はYouTubeなどの動画コンテンツが流行っていて、わざわざ本を選ぶ人が減っているのも事実です。
とはいえ、短時間でサクッと勉強できる動画や、ググったら簡単に答えがわかるネットよりも、本のほうが信頼性が高く網羅的に学べる。
これは好みの問題なので、一概にどっちのほうが良いとは言い切れませんが、僕は本から情報を得るのが良いと思います。
というのも、動画やネットからしか情報を得ていないと、自分で考えることができない人になってしまうから。
しかし、「本をたくさん読みたいけど、お金がかかって中々たくさんは買えない」という人も多いでしょう。
そういう人には、Kindle Unlimitedなどの読み放題サービスがおすすめです。月額980円(税込)で何冊でも読めちゃいますよ。
月2冊読むだけで簡単に元が取れるし、面白くなかったら読むのを止めればOK。どんどん新しい本に切り替えちゃいましょう。
「どんな本を読めばいいのかわからない」という人は、とりあえず読み放題サービスから入るのがおすすめです。
しかも、今ならKindle Unlimitedが30日間無料キャンペーン中なので、お得に始められますよ。
まとめ:読書にはメリットが多い
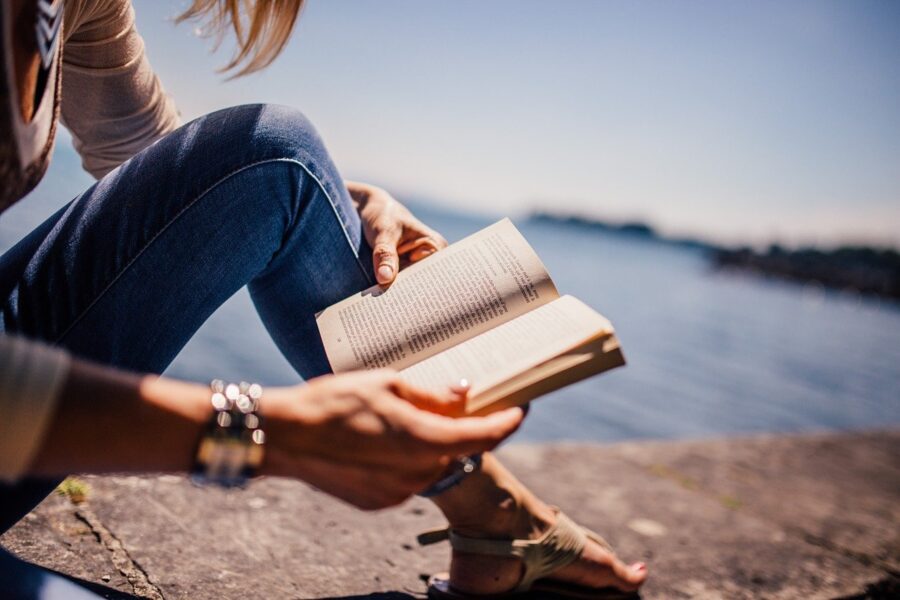
今回は、読書のメリット(効果)について解説しました。
読書にはデメリットもありますが、メリットのほうが圧倒的に多いです。
読書が苦手な人、普段本を読まない人は、さいしょに古典的名著を読むのがおすすめ。
なぜなら、長年読まれ続けているだけあり普遍的な知識が詰まっているので、読んで損することが少ないから。
そして、本は読んで終わりではなく、アウトプットして知識として身につけていきましょう。